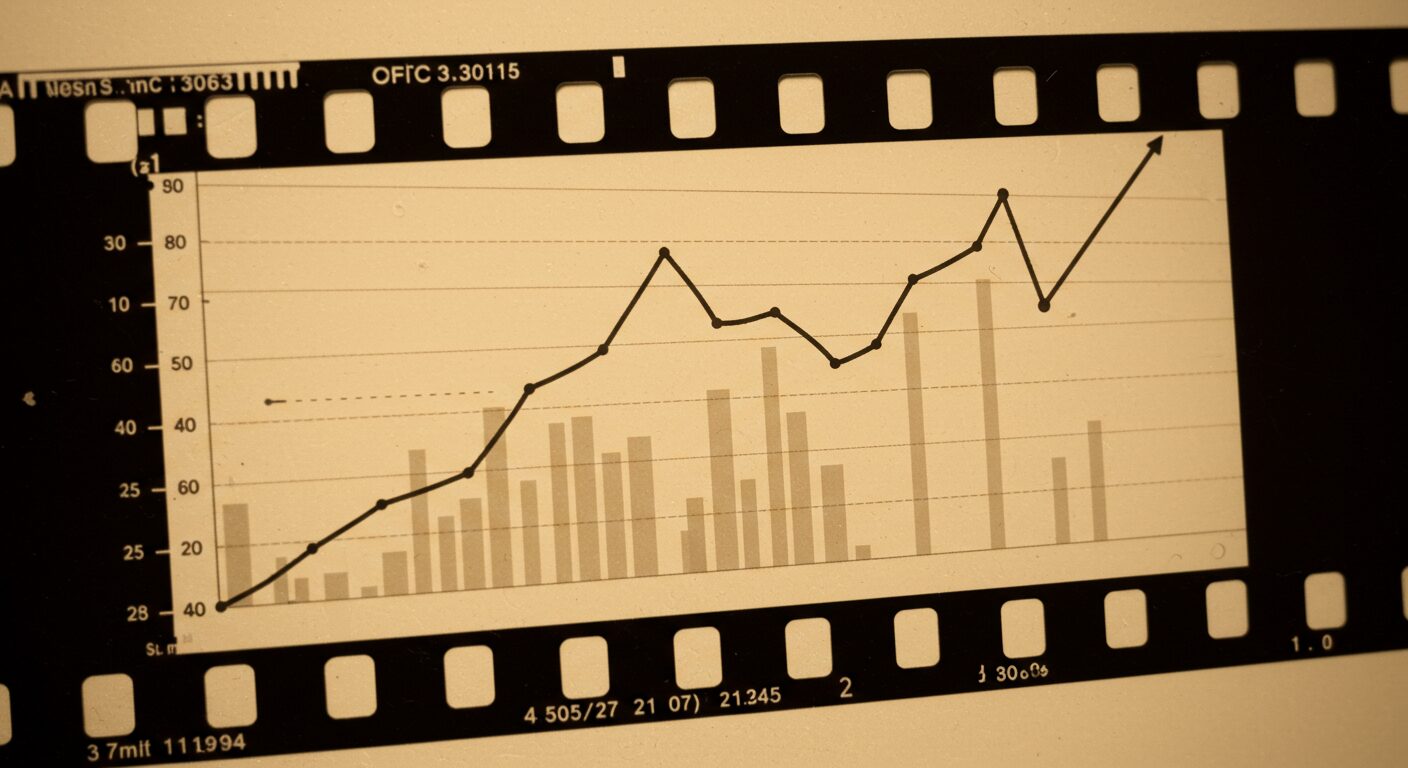ネズミがかじったと思ってた!?チーズに穴がある本当の理由とは?
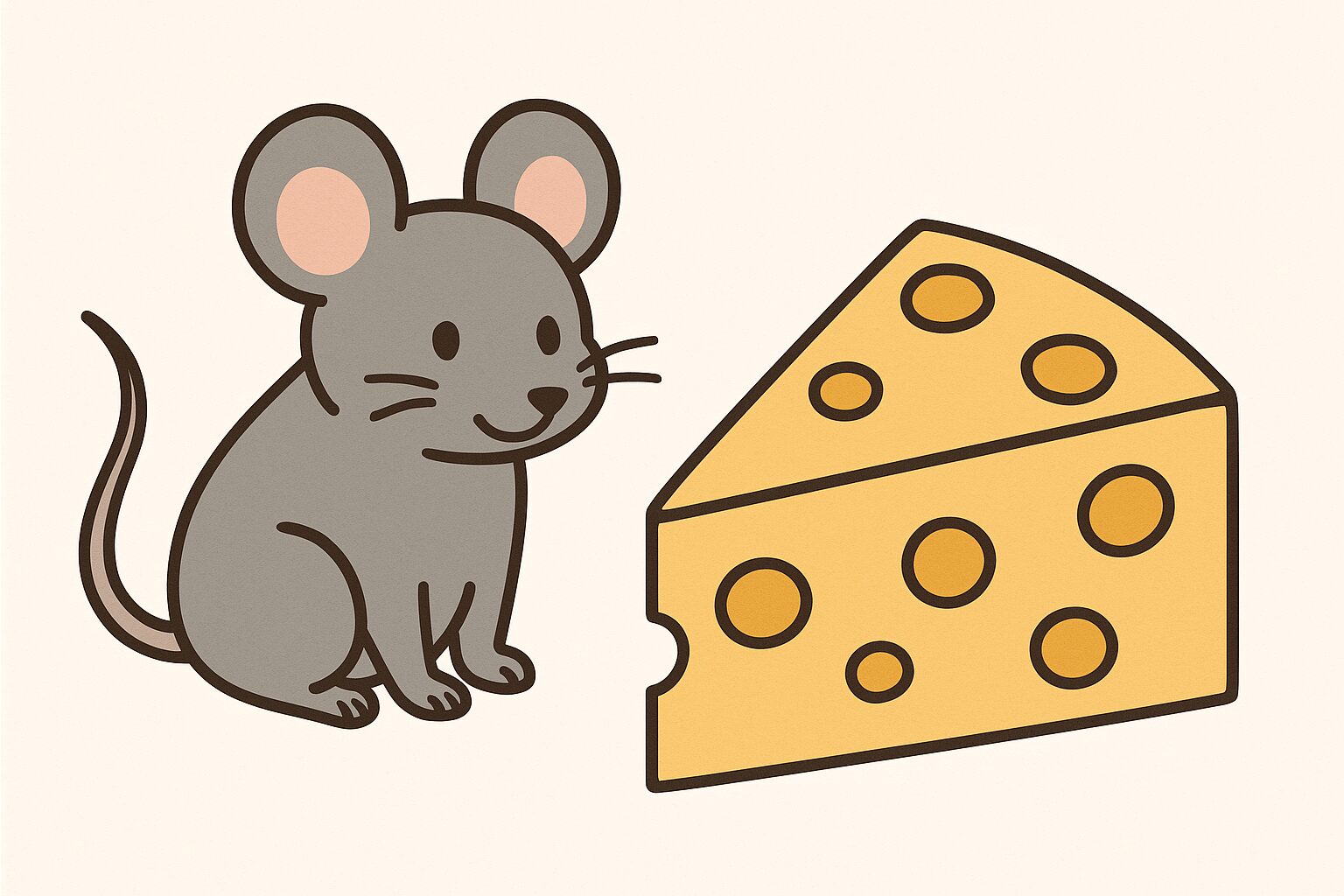
小さい頃の勘違いから始まった話
「このチーズ、ネズミがかじったの?」
子どものころ、黄色くて穴のあいたチーズを見て、そんなふうに思ったことはありませんか?実は筆者もずっとそう信じていました。あの丸い穴はネズミが残した証拠だと。
でも、大人になって調べてみると……なんとあれ、菌のしわざだったんです!
今回は、そんな「チーズの穴」にまつわる素朴な疑問にお答えします。「なぜ穴ができるのか」「どんなチーズにあるのか」「なぜ他のチーズには穴がないのか」など、知ればチーズ選びがもっと楽しくなる話をお届けします。
穴あきチーズの代表格は「エメンタール」
まず、穴があるチーズといえば、真っ先に思い浮かぶのがエメンタールチーズ。スイス原産で、アニメ『トムとジェリー』に出てくるような、いわゆる”絵に描いたようなチーズ”です。
このほかにも、穴が見られるチーズには次のようなものがあります:
- ジャルスベルグ(ノルウェー):マイルドでやさしい味わい。
- スイスチーズ(アメリカ):エメンタール風の加工チーズ。
- アッペンツェラー(スイス):風味は強め。穴は少なめ、またはほぼ無しも。
これらのチーズに共通するのは、発酵の過程で穴ができることです。
チーズの穴はどうやってできるの?
あの穴の正体は、ネズミではなくガス。
穴あきチーズには「プロピオン酸菌(プロピオニバクテリウム)」という特別な菌が使われています。この菌はチーズの中の乳酸を分解して**炭酸ガス(CO2)**を発生させます。
そのガスがチーズ内部に溜まることで、ぷくっと膨らんだ“穴”ができあがるのです。この穴は「eye(目)」と呼ばれ、チーズ職人の熟成技術によって大きさや数が調整されます。
なぜ他のチーズには穴がないの?
実は、ほとんどのチーズには穴がありません。それにはいくつかの理由があります:
1. プロピオン酸菌を使っていない
多くのチーズ(モッツァレラ、カマンベール、チェダーなど)は、プロピオン酸菌ではなく乳酸菌やカビを使って発酵させます。そのため、ガスが発生せず、穴ができないのです。
2. ガスが逃げる構造になっている
ブルーチーズやウォッシュタイプなどは、熟成の過程で内部にできたガスが外に抜けやすい構造になっています。ガスがとどまらなければ、穴もできません。
3. 熟成温度や時間が違う
穴ができるには発酵時に一定以上の温度や湿度が必要です。他のチーズは低温で熟成されたり、短期間で仕上げられたりするため、ガスがたまりにくいのです。
穴あきチーズの味の特徴は?
穴そのものに味はありませんが、穴を作る「プロピオン酸菌」が生み出す風味がチーズの味に影響します。ナッツのような香ばしさ、ほのかな甘み、まろやかなコクがあり、クセが少なくて食べやすいのが特徴です。
「チーズはちょっと苦手だけど、挑戦してみたい」という方にもおすすめです。
個人的おすすめの穴あきチーズ(日本でも買える)
- ジャルスベルグ:マイルドでそのまま食べてもおいしい。初心者にぴったり。
- エメンタール:王道の穴あきチーズ。加熱にも向いていて万能。
輸入チーズ売り場やオンラインショップで比較的入手しやすいですよ。
まとめ:穴が語る、チーズの奥深さ
チーズの穴は、菌が作り出した“自然の芸術”。 ネズミがかじったわけではなく、発酵の過程で生まれるものだったんですね。
穴のあるチーズ、ないチーズ。どちらもその製法と菌の違いが生み出す個性です。
「今日はどんな菌が活躍してるチーズにしようかな?」なんて視点で選べば、毎日の食卓がちょっとだけ面白くなるかもしれません。