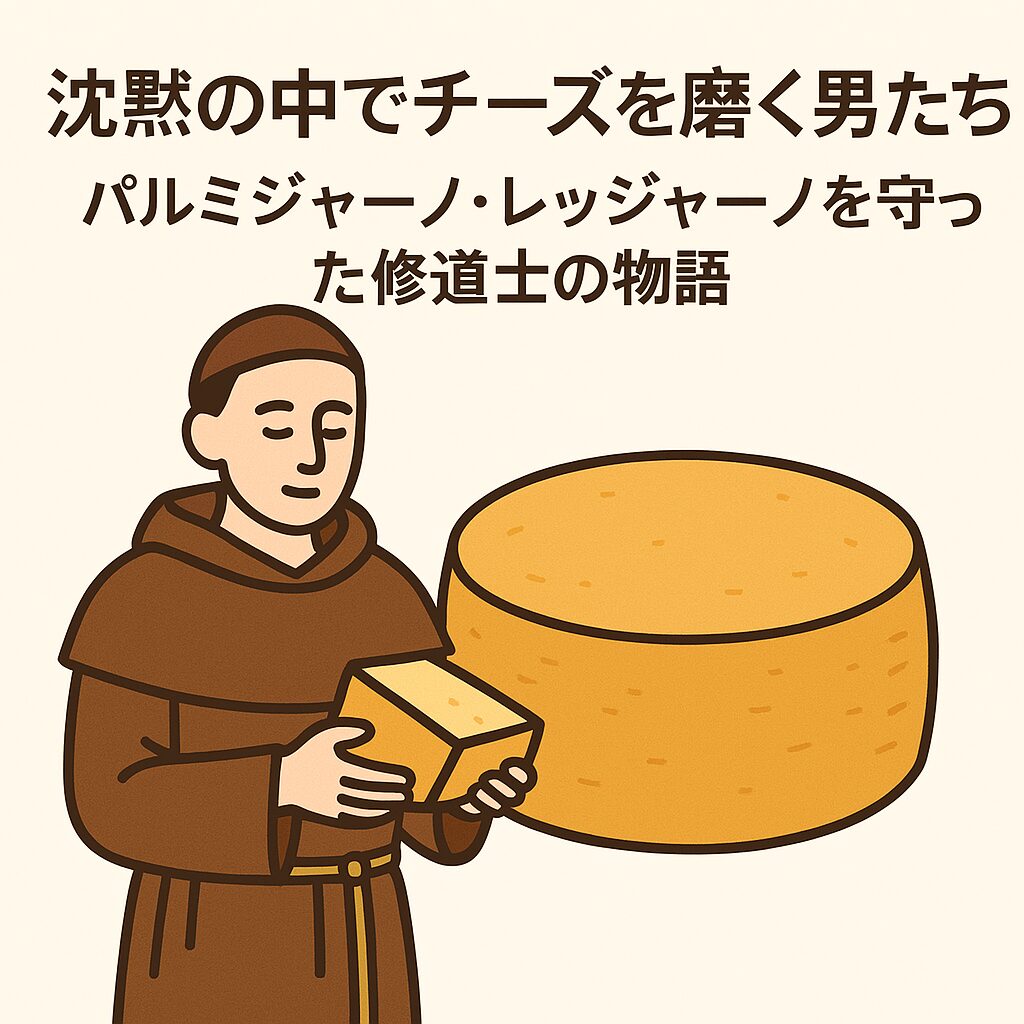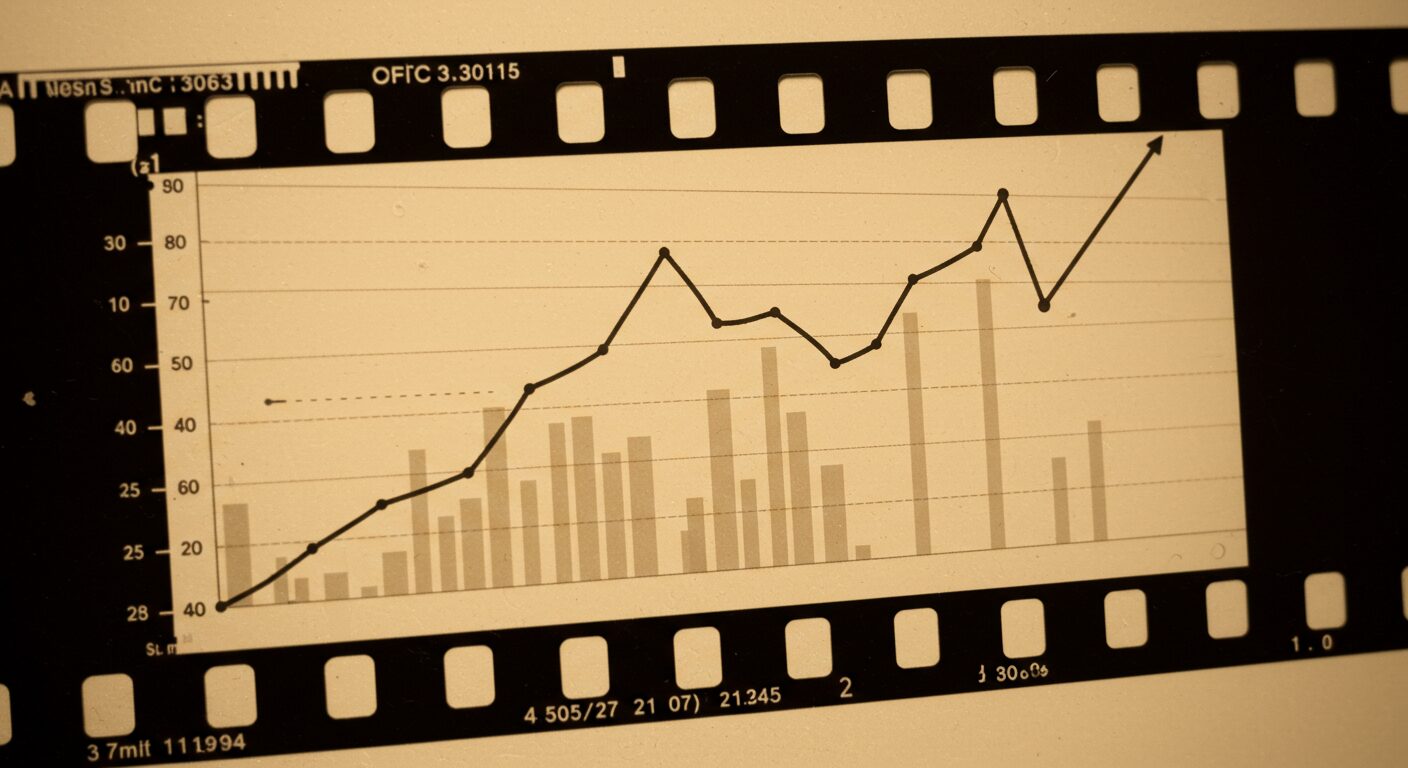昔あった「三角の牛乳」がなくなった理由とは?なぜ三角だったのか?

学校給食やスーパーで見かけたことがあるかもしれない「三角の牛乳」。
今ではほとんど見かけなくなりましたが、なぜ三角形だったのでしょうか? そして、なぜ姿を消してしまったのでしょうか?
この記事では、三角パックの牛乳の誕生とその特徴、そして消えてしまった理由について解説します。
三角の牛乳が誕生した理由
三角パックの牛乳は、1950年代から1990年代頃まで日本の学校給食などで広く使用されていました。このパックは「テトラパック」と呼ばれ、スウェーデンの企業テトラパック社が開発したものです。
なぜ三角形だったのか?
三角パック(正式には「テトラパック・テトラヘドロン型」)が誕生した背景には、効率的な牛乳の流通と保存 という目的がありました。
- 紙パック技術の進化
それまで牛乳はガラス瓶で販売・提供されるのが一般的でした。しかし、瓶は重く、輸送コストがかかる上に割れやすいという欠点がありました。
そこで、スウェーデンのテトラパック社が開発したのが、軽量で丈夫な「テトラパック」でした。 - コンパクトで省スペース
三角形のパックは、円柱型の瓶よりもスタッキング(積み重ね)がしやすく、保管や輸送の効率が良いというメリットがありました。
また、紙製のため、ガラス瓶のように洗浄する手間が不要で、使い捨てが可能という点も画期的でした。 - コスト削減と環境負荷の軽減
牛乳瓶は回収・洗浄・再利用が必要でしたが、三角パックならリサイクル不要で、製造コストも低いというメリットがありました。
こうした理由から、1950年代に日本でも三角パックの牛乳が広まり、特に学校給食では定番となりました。
三角の牛乳が消えた理由
便利だった三角パックの牛乳ですが、1990年代以降、急速に姿を消しました。その理由には、いくつかの問題点が関係しています。
1. 開けにくかった
三角パックの最大の弱点は、開けにくいことでした。
紙パックの端をつまんで開けるのですが、力加減を間違えると牛乳が飛び散ることもありました。
特に子どもたちにとっては、扱いづらく、給食の時間にこぼしてしまうトラブルがよく発生しました。
2. ストローが使えなかった
三角パックは、直接口をつけて飲むスタイルが一般的でした。しかし、衛生面を考えるとストローを使って飲める方が好まれるようになりました。
その結果、ストローを刺しやすい四角い紙パック(ブリックパック)が普及し、三角パックは徐々に廃れていきました。
3. 陳列や流通の問題
三角パックは積み重ねやすい反面、店舗の冷蔵ケースでは陳列しづらいという問題がありました。
四角い紙パックなら棚にピッタリ収まり、消費者も手に取りやすいため、スーパーでは次第に四角いパックが主流になりました。
4. 紙パックの技術向上
当初、三角パックは牛乳の保存に適していましたが、技術が進歩したことで、四角い紙パックでも長期間の保存が可能になりました。
こうした技術革新によって、三角パックの優位性がなくなったことも、消えてしまった理由の一つです。
三角パックの牛乳はもう飲めないのか?
現在ではほとんど見かけなくなった三角パックの牛乳ですが、完全になくなったわけではありません。
例えば、レトロなデザインの商品として限定販売されることもあります。
また、一部の海外地域では、今でも三角パックの牛乳が流通しているところもあります。
さらに、牛乳以外の飲料では、テトラパックの技術を活かした紙パック飲料がまだ使われています。
例えば、豆乳やジュースなどは、テトラパックの技術を活かした四角いパックで販売されています。
ガチャガチャのおもちゃも販売されています。
まとめ
かつて学校給食の定番だった三角の牛乳は、
- 軽量で丈夫、輸送しやすい
- コストが低く、環境負荷も少ない
といった理由から普及しました。
しかし、
- 開けにくい
- ストローが使えない
- 店舗での陳列がしにくい
- 四角い紙パックの技術向上
といった理由で姿を消しました。
現在ではほとんど見かけなくなりましたが、レトロなデザインとして復活する可能性もあります。
昔の学校給食を思い出しながら、もし見かけたらぜひ飲んでみてくださいね!